
|
生活設計を立てるうえで最も重要かつ大切なものに貯蓄があげられます。
金融自由化が進展するなかで、金融機関経営の健全性に対する関心が高まり、低金利のもと有利な貯蓄行動を模索する動きもみられます。
同調査による貯蓄の種類別保有状況をみると、「預貯金」(55.0%)が最も多く、平成6年(’94)以降3年連続して増加しており、次いで「生命保険・簡易保険」(20.2%)の順になっています。
また、「個人年金」の構成比が4.6%となっており、平成元年(’89)の1.7%に比べ2.7倍に増加しており、今後1年間で最も重視する貯蓄の種類としても5.9%で、「預貯金」(66.2%)、「生命保険・簡易保険」(12.8%)に次いで3位となっています。(図17)
これは、公的年金制度の度重なる改正と先行きの不安感から、高齢化社会に対応する生活費の確保として自助努力による私的年金への加入を実行、検討する人が増えていることが窺えます。
また、「貯蓄の目的」(3項目以内での複数回答)についてみると、「病気や災害への備え」(69.7%)を挙げる世帯が最も多く、次いで「老後の生活資金」(53.9%)、「こどもの教育資金」(33.1%)、「住宅取得・増改築資金」(20.3%)などとなっています。(図18)
さらに、「借入金の有無」についてみると、借入金の「ある」世帯は48.3%となっており、これまでの調査で最も高い水準となっており、その目的としては「住宅の取得・増改築資金」を挙げる世帯が61.0%と他を大きく引き離しています。
生活設計における「経済的豊かさ」と「心の豊かさ」についてると、経済的豊かさを「実感している」世帯の4割弱(36.3%)に対して、「実感していない」世帯が6割(61.9%)を超えており、心の豊かさでは「実感している」世帯が全体の64.6%と、「実感していない」世帯(34.1%)のほぼ2倍という結果となっており、経済的な実感を感じられず不安な面を現しています。
このように、将来の生活に対する不安は、一層進む高齢化社会と社会保障費等のバランス、停滞する経済動向、金融機関の破綻などを起因としてますます増してきており、障害者と家族をとりまく環境にも大きな影響を及ぼしてきています。
図16 「生活設計」を現在立てていない理由
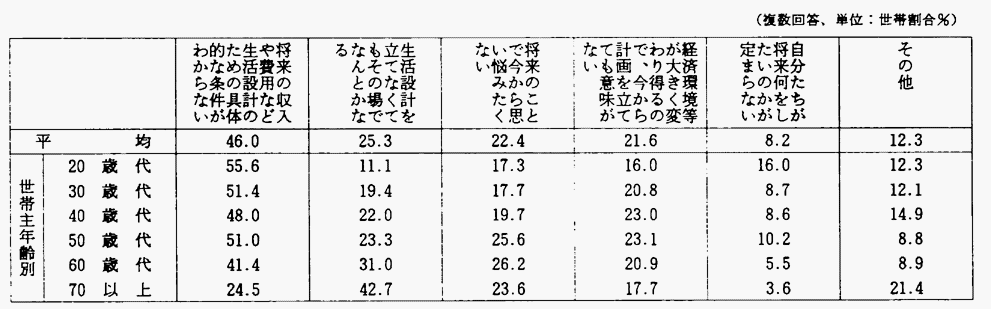
前ページ 目次へ 次ページ
|

|